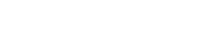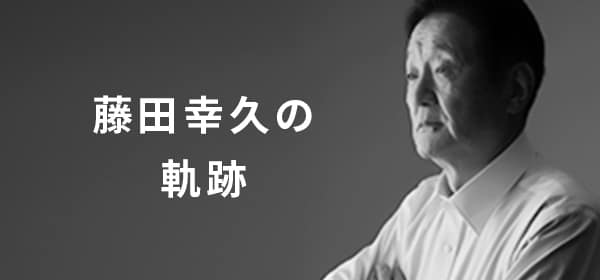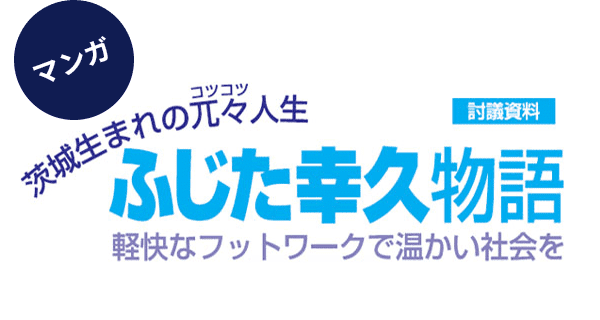ブログ
日英の和解会議で講演2025年08月11日
8月11日英国Newburyで講演しました。8月15日の対日戦勝80周年記念日に向けた行事(JV 80イベント)の一環です。「復讐と和解:戦後、次は何か?」がテーマで、英国陸軍で20年間在職後、West Berkshire 州議会議長を務めるTony Vickersさんが主催しました。約70名が参加しました。
(写真:左からHoward Grace、藤田幸久、Tony Vickers、Edward Vickers)
Vickersさんは、「私たちは政治指導者たちへの絶望と信頼の喪失を感じています。そして、未来への希望と信念を取り戻したいのです。今日話をする人々は、平和のために様々な形で活動しており、その話を聞くことは非常に感銘深いものでした」と趣旨を述べました。
司会は、BBCおよび日本の複数のメディアで活躍したBernard Clarkさんが務めました。長崎の原爆投下を記念する式典で、子どもたちと一緒に参加したことに深く感動したと語りました。
私は50年前に、国際IC親善使節「Song of Asia」でアジアの青年達と世界を歴訪し経験を述べました。「アジアの青年達を知れば知るほど、父の世代が戦争中にアジア各地で行ったことについて、私はいかに無知だったかに気づきました。香港の友人から「戦時中の日本の残虐さ」を聞いたときには衝撃を受けました。その後さらに学ぶにつれて、アジアの隣人たちとの和解を人生のライフワークとしようと決意しました。」と述べました。
そして、各国の元捕虜と日本の元兵士との交流や和解活動のお手伝いをしてきたことを紹介しました。シンガポール陥落時の杉田一次大佐(後に自衛隊陸上幕僚長)が国際IC(MRA)会議で元英国兵に謝罪したことから、この元兵士は広島や長崎の慰霊式典に参加するなどの和解活動を始めたこと。
元兵士のウェールズの労働組合指導者がスイスのIC(MRA)会議で日本との和解を果たし、東京で日産自動車の石原俊社長と対話したことを通し、日本の住友金属の工場をウェールズのLlanwernに受け入れることを歓迎する役割を果たしたことなどです。
続いてTony Vickersさんの息子の九州大学のユネスコ「平和・社会正義・地球市民教育」担当のEdward Vickers教授が話しました。夫人が日本人の彼の家族は、日本とイギリス双方の文化に親しんでいます。彼の発言は、以下の通りです。
「多くの中国人や韓国人に反日感情を抱かせてしまっていることが、国際関係に影響を及ぼしています。平和への誓いは日本人のアイデンティティの中心となっていますが、それは「原子爆弾による攻撃を受けた唯一の国として、日本人ほど戦争を体験した国民はいない」という認識に基づいています。他方、日本の歴史教科書は、南京での日本軍による中国人虐殺のような出来事をほとんど触れずに済ませています。
イギリスでの歴史教育は14歳までしか必修ではなく、多くの教師が教えやすい部分を選んで教え、負の歴史を避けています。これが「勝利主義的な歴史観」を生み出しています。日本と同じように、私たちも歴史的・文化的無知という危険なカクテルを抱えています。自国の特別な国民的資質を信じることと相まって、それは自らが抱える問題を敵対する外国や外国人のせいにする傾向を強めています。もし私たちが再び世界大戦を避けたいのであれば、第二次世界大戦を人類が共有する弱さを思い起こさせる冷静な物語として語り継ぐ必要があります。」
その後、多くの参加者が考えや経験を述べました。軍務経験が豊富な人々、市民活動のリーダー、元軍隊の牧師などです。過去の過ちを隠すことは、それを繰り返す道を開く、という認識が広く示されました。一方で、現在は1930年代に戦争を引き起こしたような国家主義的政策を唱える人々が少なくなく、しかもそれを実際に実行している政府もあると指摘されました。
教育の役割が重要だという点で幅広い合意がありました。フランスとドイツは70年間に3度も大きな戦争を戦いましたが、現在では両国の多くの学校が、両国の歴史家が共同で執筆した歴史教科書で歴史を教えていることも紹介されました。
Tony Vickersさんは、「The Hardest Bridge(最も困難な橋)」という、北アイルランドにおける和解を扱った映画の上映をきっかけにこの会合のアイデアが生まれたと説明しました。そして、その映画を観て、和解のメッセージ、赦しの力が、今日私たちが直面している多くの紛争にも応用できると考えたのですと述べました。


- アーカイブ
-